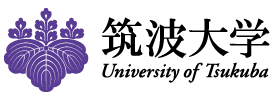形質転換植物デザイン研究拠点

「形質転換植物のデザイン ー基礎研究から実用化に向けてー」
今回のシンポジウムでは平成22年度から研究を進めている課題の中から5課題選んでその成果を報告した。
また、奈良先端技術大学院大学の横田明穂先生と農業環境技術研究所の吉村泰幸先生をゲストスピーカーにお迎えしてご講演いただき、遺伝子組換え植物の今後について総合討論した。
なぜGMエネルギー植物なのか
奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 横田 明穂

1.はじめに
日本の国土面積は3,780万haで、その内農耕利用可能全面積は610万haである。関東以西では冬も耕作が可能なので、最大耕作利用面積は850万haになる。しかし、実際は遊休地や冬場の休耕などで、稲作に180万ha、稲作以外に320万haを使っている。これだけでは1億2700万人の食料はまかなえず、海外から1,200万haで耕作された農産物を輸入している。その結果、我が国の食料自給率は、40%弱(エネルギーベース)で推移している。耕地面積が不足している我が国がこの現状を改善する手立ては、世界の食料生産を向上するための科学技術によって世界を支援しつつ、栽培国の余剰分を輸入する以外に恒久的な解決策はない。では、作物も含めて、植物の生産力にはどれほどの余力があるのか、次に考えたい。
植物の生産を支える光合成にとって、地球に届く太陽エネルギー量の1/3~1/2で十分である。この光の量で実測されている最大光合成CO2固定速度は60 mmol/m2/sである(Science, 1976)。この速度で半年間作物を栽培したとすると、50~100 t/ha程度の生産が可能になる。ドイツのジャガイモ生産性は44 t/ha/年である。乾物重では22 t/ha/年となる。したがって、本来土地利用効率とハーベストインデックスが高い植物は植物の生産力の上限を決める研究には非常に魅力的である。多くの作物の生産性は2~10 t/ha/年である。 私たちは、このような観点から、元来生産性が非常に高いイモ類を使ってその生産性の上限をさらに向上させるALCAイモプロジェクトを開始した。多くの作物は、4億年ほど前に陸生を始めたシダ植物や裸子植物から派生し、2000万年位前に品種として独立したものが多い。したがって、このような作物種の遺伝子群はすべてこれらの先祖植物由来であり、先祖植物以外の他生物由来の遺伝子は全く使えない。その後の生育環境への適応過程で個々の遺伝子をより進化させてきたと思われるが、そこにも光合成を行っている葉にも、光合成産物を貯蔵する貯蔵組織にも深刻な限界があった。この限界こそが我々のALCAイモプロジェクトのターゲットである。以下に、我々のALCAイモの分子育種研究の立ち上がってきた経緯、研究の目標と内容などについて紹介する。
2.ALCAイモプロジェクト研究の目標と内容
1980年代の分子生物学的手法による遺伝子発現抑制技術の開発を受け、多くの光合成代謝遺伝子の重要度が解析された。CO2の固定及び代謝反応を担うカルビン回路では、ルビスコ及び2つのホスファターゼがまさしく光合成全体の律速(光合成速度制限)酵素であった。これら2つのホスファターゼは固定CO2から次のCO2固定の受け手の化合物であるリブロースビスリン酸(RuBP)の再生に関わる酵素である。一方、ルビスコが機能を十分に発揮するには、RuBPで活性化されたルビスコ活性化酵素によって活性化を受けなくてはならない。実際、タバコのカルビン回路で高活性のラン藻型ホスファターゼを機能させると、RuBPのレベルが上昇し、さらにルビスコが活性化されて光合成CO2活性が向上することを、我々は見い出した(Nature Biotechnol 2001, PCP 2008)。この遺伝子がこれまでで最も強力な葉の光合成機能改良遺伝子である。ジャガイモの葉でこの酵素を機能させると、葉の光合成は20~30%上昇した。
ジャガイモの貯蔵組織である塊茎の貯蔵能力強化のための戦略は、意外な研究展開によってもたらされた。カラハリ砂漠原産の野生種スイカは地中深く根を伸ばして地下水を確保する能力に長けていることが生態学的によく知られていた。我々の研究でも、野生種スイカが土壌乾燥を感知すると根を急速に発達させることが確認された。そこで根の急速な発達時に発現する遺伝子の探索から、DRIP-49を見出した。このタンパク質はすべての真核生物で細胞分裂や細胞質と核間の転写因子などの輸送に関わる生存に必須のものである。野生種スイカにはこれに加えてもう一種存在し、土壌乾燥時に根端や側根生長点で強く発現していた。この遺伝子を35Sプロモーター制御下でシロイヌナズナやジャガイモに導入すると、これらの植物の根の強く発達した。また、このジャガイモを土壌でポット栽培すると、ベクターコントロールと比べ葉の光合成CO2固定速度は20~30%上昇した。
以上の結果は、ジャガイモの生産性は、これまでの作物学の常識を覆し、ジャガイモの場合ソース葉及びシンク組織双方が独立に生産性の制限要因になっていることを示している。また、これら両遺伝子を同一植物体で機能させると、葉の光合成は他の場合と同様に20~30%上昇したが、塊茎重量は3.5倍の上昇となった。このジャガイモの生産性向上が野外圃場で再現された場合、ジャガイモの乾物重は70 t/ha/年に達すると予想される。これはまさしくほぼ地球上の植物の最大生産性に近い値が達成されると考えられ、将来のエネルギー、資源、食料などに有望な植物になる。これが我々のALCAイモプロジェクトである。

遺伝子組換え作物の生物多様性影響評価 -とくに競合と交雑について-
独立行政法人農業環境技術研究所 生物多様性研究領域 吉村 泰幸
遺伝子組換え(GM)作物について、主に懸念される事項は、食べて安全か、環境に安全か、であり、食の安全については、「現在、取り扱われているGM作物を含む食べ物は、GMでない同等品と同じくらい安全」であることが、FAO/WHOコーデックス食品企画委員会で評価されている。環境(生物多様性)への影響については、国内では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」が2004年2月19日より施行され、それまでのガイドラインによる環境安全性の評価から周辺生物相に対する生物多様性影響評価が法律により義務付けられた。カルタヘナ法では、GM生物の使用形態を2種類に分けて評価している。一つは「第1種使用」と呼ばれ、環境中への拡散を防止しないでGM生物の使用を行う場合で、食料や飼料としての運搬や農地での栽培がそれに相当する。もう一つは「第2種使用」で環境中への拡散を防止しつつGM生物を使用する場合で、拡散防止措置がとられている実験室や工場での使用がそれに相当する。GM作物の第1種使用規程の承認申請を行おうとする事業者は、まず、申請するGM生物の生物多様性影響評価書を、主務大臣及び環境大臣に申請する。次に、法に基づき予め公表されている名簿に登録されている学識経験者から構成される「生物多様性影響評価検討会」において生物多様性影響評価書等の内容の妥当性について意見が聴取され、ウェブサイト等で公表されるとともに、その後提出されたパブリックコメントを踏まえて承認の可否が検討され、その結果が申請者に通知され官報によって告示される。
カルタヘナ法ではGM作物の第1種使用規程の承認申請に必要な生物多様性影響評価は、特に野生生物への影響評価に重点がおかれ、(1)競合における優位性(在来の生物と競合する場合の影響)、(2)交雑性(遺伝子組換え生物が在来種と交雑する場合の影響)、(3)有害物質の産生性(遺伝子組換え生物が有害物質を生み出す場合の影響)、という3つの観点で検討される。交雑性についての評価は、まず、交雑する近縁種が国内に存在するかどうかで判断され、交雑する相手のいないイネ、トウモロコシ、ワタ等では、生物多様性影響(交雑性)が生じる恐れはないとして利用可能となる。交雑する相手が存在する場合には、その野生生物を特定し、どのような影響をどの程度受けるのかを調べ、影響があると判断されれば、利用不可となる。日本を含む中国、韓国、ロシアの一部の東アジアには、ダイズの近年野生種であるツルマメが存在し、当研究グループでは、圃場条件下においてGMダイズとツルマメがどのくらい交雑するのかを調査した。本研究の結果、日本においてGMダイズの周囲にツルマメがあれば、自然交雑する可能性はゼロではない。しかしながら、本実験では、両種の開花期をより近づける処理を行った条件での試験であり、また、交雑のほとんどは、両種がからみついた条件で発生しており、通常の雑草管理を伴う栽培であれば、自然交雑が起こる可能性は極めて低いこと。また、適当な隔離距離を保つ、あるいは、GMダイズを早期に栽培する等の手法で、GMダイズからツルマメへのジーンフローを減少させることができることも明らかとなった。
競合における優位性については、現行の評価システムでは、低温・高温に対する耐性、越冬性、越夏性等について、GM作物が生物多様性を減少させる可能性が宿主である非GM作物と比較して違いがないか、またはその違いが当該作物の一般に持つ特性の範囲内に収まっているか、について実験的または文献情報により検討される。しかしながら、非生物的ストレス耐性GM作物は、宿主である非GM植物と比較して有意な差が認められる可能性があり、生物多様性影響評価検討会に出席する有識者の見識、経験によって判断される部分が大きいと考えられる。 本講演では、今後、市場化されるであろうストレスに対する耐性を高めた作物についてはどのような評価をすればよいのか、現在米国で申請されている乾燥耐性GMトウモロコシの例を紹介しながら、今後日本でどのように生物多様性影響評価の一項目、「競合の優位性」を評価すればよいのかを考えてみたい。

図. 遺伝子組換えダイズとツルマメとの交雑実験の様子
吉村先生には、シンポジウムに参加された感想をいただくことができたので、以下の通り紹介したい。
『「植物はやっぱり面白い、研究者は、様々な植物をじっと観察しもっと自由な発想で研究を行うべきだ」、と横田先生のお話を聞き、改めて思いました。また、私の研究は、開発から実用化の流れの中で出口の部分にあたりますが、私たち環境影響評価を行う研究者と新しい植物を作る研究者との間のコミュニケーションがもっと必要で、そうすることでより効率的で、スピーディーな海外に負けない研究ができるのではないかと感じました。』
- 2011/07/12 筑波大学遺伝子実験センター 形質転換植物デザイン研究拠点 公開シンポジウム2
「形質転換植物のデザイン —基礎研究から実用化に向けて—」 - ポスターPDFはこちら